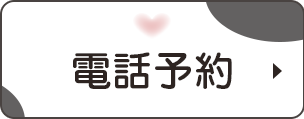4月 妊娠中に気をつけたいこと
2024年04月1日
こんにちは! 船橋こども歯科の中谷です。
少しずつ暖かい季節となってきました。
気温の変化には注意してお過ごしください。
今月のお話は「妊娠中に気をつけたいこと」についてです。
①バランスの良い食事を心がけましょう
お腹の赤ちゃんは、母親の身体から必要な栄養素を受け取ります。
お母さん自身が健康で暮らせるように、楽しく、規則正しくバランスの取れた食事をすることが大切です。
この規則正しい食習慣は生まれてくる子供の食習慣の形成にもつながります。
②偏った食べ方には注意しましょう
妊娠中に牛乳や卵など普段より多くとる方がいらっしゃいます。
特定の食材を摂取することで、子供がアレルギーを持って生まれてくる
危険性が高くなります。バランス良く食事をしましょう!
4月 こども歯科イベントのお知らせ
2024年03月2日
こんにちは!
船橋こども歯科では、4月にイベントを行います。
今回の内容はこちら!
「歯科検診の謎を知ろう!」
・歯科検診で先生は何を見ているの?
・先生が言っている言葉を知ろう!
・検診で使っている道具を使ってみよう!
・歯磨き練習でクラス1バンになろう!
詳細は下記をご参照ください。皆さまのご参加をお待ちしております!

2月イベントのお知らせ
2024年01月5日
こんにちは!
船橋こども歯科では、2月にバレンタインイベントを行います。
今回の内容はこちら!
・よく聞く「キシリトール」について、聞いて、見て、食べてみよう!
・かわいいオリジナルの歯をつくってみよう!
・自分で「フロス」ができるようになろう!
詳細は下記をご参照ください。皆さまのご参加をお待ちしております!

歯に関連する栄養素
2023年08月1日
こんにちは!管理栄養士の熊川です。
待ちに待った夏休みが始まりました!
楽しい予定がたくさんある夏休みですが、生活リズムを崩さないように注意しましょう。
楽しかった夏の思い出の話をたくさん聞かせてくださいね!
今月は歯に関連する栄養素についてのお話です。
硬い骨をつくるのはカルシウム。エネルギーになるのは炭水化物。
では、歯に関係する栄養素はどんなものがあるのでしょうか?
☆歯を作るために欠かせない栄養素
カルシウム:硬い歯の表面(エナメル質)を作ります。 例:小魚、海藻、牛乳、乳製品
たんぱく質:歯の内側(象牙質)を作ります。 例:肉類、魚類、卵、大豆、乳製品
ビタミンA、C、D:エナメル質や象牙質をつくる働きを助けます。
例:レバー、にんじん、赤パプリカ、キウイフルーツ、きのこ類
☆歯をきれいにしてくれる栄養素(直接清掃性食品と呼ばれます)
食物繊維:繊維質を噛むと歯の表面とこすれて汚れを落としてくれます。繊維は歯と歯の間にはさまりやすいので、フロスは忘れずに!
例:こんにゃく、ごぼう、レタス
☆他にも…
他にも歯茎を健康に保つためにはビタミンC、口内炎予防にはビタミンBなど様々な栄養素が関わっています。
特に子供の歯が生える時期(生後6ヶ月〜2、3歳ごろ)、大人の歯が生える時期(6歳〜12歳ごろ)は栄養素が不足してしまうと歯がもろくなってしまうことがあります。
大人の歯が生えてから歯質を変えるのは難しいです。歯が作られる時期にバランスよく食事ができるように意識してみましょう!
※歯が生える時期には個人差があります。
歯の種類について
2023年04月1日
こんにちは!歯科衛生士の尾島です。
寒さも和らぎ、温かい春の日差しの中新年度がスタートしました。
また一つお兄さん、お姉さんになりドキドキ、ワクワクしている方も多くいると思います。
新年度も気持ちよく過ごせるよう、体調管理に気をつけながら過ごしましょう。
今月は歯の種類についてのお話です。
皆さん、歯には1つ1つ名前がついておりそれぞれ重要なはたらきがあることを知っていますか?歯は私達の健康を守るために必要不可欠です。
前歯
前歯は平べったくシャベルのような形をしていて、食べ物を噛み切る時に使う歯です。
硬い食べ物や柔らかい食べ物を食べる時は前歯で噛み切るようにしましょう。
犬歯
犬歯は牙のような形をしています。歯の中では一番強い歯とも言われています。
奥歯
奥歯は食べ物をすりつぶす役割をしておりゴツゴツした石のような形をしています。
前歯に比べて寿命が短いので丁寧に歯磨きをすることが大切です。
このように歯にはそれぞれ役割があります。形や大きさも1つ1つ違うので
是非どんな形をしているのか観察してみてください!
また、歯の1つ1つの名前は院内新聞に詳しく載っているので是非御覧ください!
普段、私達が食事を美味しく食べられているのは歯が健康だからです。
特に大人の歯は、こどもの歯と違ってこの先何十年も使う歯です。
今からしっかりと歯磨きをする習慣をつけてむし歯にならないようにしましょう。
230323_12_院内新聞2023年4月号(大人の歯の種類) (5) 
食中毒について
2022年09月1日
こんにちは。管理栄養士の熊川です。
まだ暑さも続いていますが、いかがお過ごしでしょうか?
楽しかった夏休みもあっという間に終わり、新たに新学期が始まります。
朝晩の気温差も生まれてくる頃です。体調に気をつけながら過ごしていきましょう!
今月のテーマは食中毒です。
食中毒というと梅雨や夏頃をイメージしますが、実は秋も要注意です。
その理由として、
①夏バテをして免疫力が低下
②1日の気温差が大きく、体調を崩しやすい
という点があります。
特に子供の場合、大人と比べて免疫・消化機能が十分でないため、更に注意が必要です。
食中毒を予防するための4つのポイントを紹介します。
①手指、また食材をよく洗い食中毒の原因菌をつけない
②料理を作ったまま放置せず食中毒菌を増やさない
③よく加熱処理をして食中毒菌をやっつける
これらはよく言われている3つの原則です。
これらにに加え、歯科的な目線で見ると
④よく噛むこと
も食中毒の予防には大切です。
よく噛んで食べ物を細かくすることで胃液(※1)が食べ物に触れる面積が広がり、細菌が腸に届いてしまう前にやっつけることができます。
胃液だけでなく、唾液(※2)にも殺菌作用があります。日頃からよく噛むことを習慣づけましょう。
※1 胃液は強酸性のため、ほとんどの菌が死滅する。
※2 唾液に含まれる酵素による。
元気な心と体で新生活をスタート!睡眠の大切さ
2022年03月4日
皆さんこんにちは!管理栄養士の杉浦です。
新年を迎え、早くも2か月が過ぎました!
もうすぐ進級・進学など新しい環境を迎える人も多いのではないでしょうか?
元気に楽しく過ごせるように、今回は睡眠についてご紹介します★
睡眠って、なぜ大切なの?
睡眠は私達の体や脳を休ませるので、疲労を回復してくれます。
体に蓄積された不要なものを出してくれたり、免疫機能、情報処理能力などを高めてくれたりと、睡眠には重要なはたらきがあります!
睡眠がとれている様子
睡眠がどのくらい必要かは人によって違いますが、足りている場合は以下のような様子が見られます。いかがですか?
◆すぐ眠る、ぐっすり眠る
◆目覚めが良い(布団からすぐ出る)
◆朝の機嫌が良い
◆日中の眠気の訴えが無い
◆週末に遅くまで寝ない、など💡
何時に寝れば良い?は「何時に起きる必要がある?」で解決!
「保育園や幼稚園、小学校には何時までに行く?→身支度にかかる時間はどのくらい?」と逆算していくと、寝る時間と起きる時間の目標が決まります。特に、小学生になると朝起きる時間がグッと早まる傾向があります。時間を変える場合、まずは30分スケジュールをずらし、慣れてきたらさらに30分など試すのがオススメです!
ところで3月といえばひな祭りですね!
2月下旬頃~、買い物へ出かけた際に「ひなあられ」の売り場を目にする機会も多かったのではないでしょうか?この「ひなあられ」には「娘の健康を祈願する」という意味が込められています。知っていましたか?是非お子さんにも伝えてみましょう!
意味を知って食べると、また違った美味しさを感じられそうですね。
食べ終えた後は、お口の中をキレイにするのも忘れずに♥
むし歯になりやすい食べ物
2022年01月5日
こんにちは、船橋こども歯科の宮内です。
「あけましておめでとうございます!」
子どもたちの元気な声や挨拶と共に、新しい年がスタートしました。
皆様にとって笑顔あふれる1年でありますように!本年もどうぞよろしくお願い致します。
さて今月は、むし歯になりやすい食べ物についてお話しします。
皆さん、むし歯になりやすい食べ物と聞いて何を思い浮かべますか?
チョコやアメなど甘い食べ物を思い浮かべる人が多いと思いますが、これらの食べ物にはある共通点があります!
むし歯になりやすい食べ物その1
「ネバネバして歯にくっつきやすいもの!」
例えばキャラメルやグミなどがあります。
むし歯になりやすい食べ物その2
「甘いお砂糖が沢山入っているもの!」
例えばチョコやラムネ、ケーキなどがあります。
むし歯になりやすい食べ物その3
「口の中に長く留まりやすいもの!」
例えばジュースやアメなどがあります。
また今は、やわらかい物を食べる事が多いと思います。
想像してみてください!
ナイフでりんごを切ったとします。
ナイフはあまり汚れません。
今度はナイフでケーキを切りました。
そうするとナイフにべったりと汚れがつきます。
このナイフがそのまま私達の歯です。
このようにケーキを切るとナイフにべったり汚れがつくように、歯も汚れます。
固い食べ物に比べてやわらかい食べ物は歯に汚れがつきやすいので、むし歯にもなりやすいです。
むし歯になりやすい食べ物を食べてはいけない、というわけではないですが、
ダラダラ食べをしないこと!
時間を決めて食べること!
食べたら歯磨きをすること!
これらのことに気をつけながらバランスよく摂取し、健康な歯と体を保ちましょう。
また、当院では砂糖不使用のチョコやグミを販売しております。
お子様のご褒美やおやつに是非お試しください!
クリスマスイベントのお知らせ
2021年11月2日
12月は船橋こども歯科でクリスマスイベントを開催致します!
お日にちの合う方は是非ご参加下さい!!
イベントは完全予約制です。お電話お待ちしております!

糖を摂取するとどうなるの?
2021年10月1日
皆さんこんにちは!
船橋こども歯科衛生士の安藤です。
秋に近づきだんだん寒さを感じる時期になってきましたね…
皆様気温の変化に体調を崩さないように気をつけてください☻
私は最近、朝の寒さに負けて愛犬が寄ってくるのでとっても幸せです。
今月は糖を摂取するとお口の中はどうなるのかについてお話します。
「甘いものは回数減らして下さい~」「ジュースはお菓子と同じですよ~」
こんな言葉聞いたことありませんか?
私自身担当した患者さんにお伝えすることが多々あるなと感じます。
糖を取らない!は難しいですがむし歯にならないように糖と付き合うことが大切です。
そのためにまず皆様に知っていただきたいことが2点あります。
- お口の中は中性がベストな環境
- お口の中が酸性に傾くと歯が溶ける
なんとなく想像しづらいと思うのですが例えば…
朝の8時に朝ご飯を食べるとまずお口の中が酸性に傾きます(1回目)
↓30分~60分で中性に戻ります。
12時頃にお昼ご飯を食べるとお口の中が酸性に傾きます(2回目)
↓30分~60分で中性に戻ります。
15時頃にお菓子を食べてお口の中が酸性に傾きます(3回目)
↓30分~60分で中性に戻ります。
18時頃に夜ご飯を食べてお口の中が酸性に傾きます(4回目)
このように糖が含まれる食べ物や飲み物をお口に入れることで1日に何度もお口の中が酸性に傾きます
更にプラスしてジュースを飲んだり、ちまちまお菓子を食べるとさらに酸性に傾く回数が多くなります。
酸性なる時間が増えれば増えるほど歯が溶けやすくなります。
特にだらだら食べはお口の中が中性に戻らずにずっと酸性に傾いたままになってしまうので
常に歯が溶けやすい環境を作り出してしまいます。
何を摂取したかも大切ですが、まずはお菓子だけではなく、お食事や飲み物も視野に入れて
1日で何回お口の中に糖を摂取していたかを数えて習慣を見直してみてください(^^♪